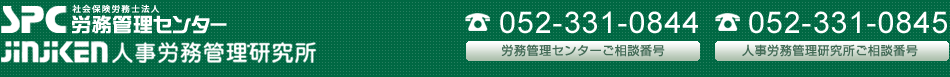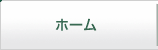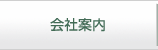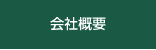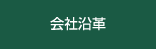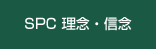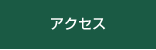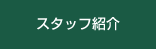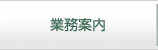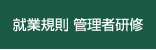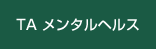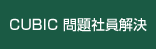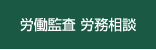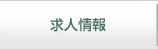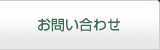期間の定めのある労働契約と有期雇用
2016/03/23
今回も、労働契約法の条文をご紹介しながら、関連判例をみていきたいと思います。
第4章は、期間の定めのある労働契約です。
第17条(契約期間中の解雇等)
第18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第19条(有期労働契約の更新等)
第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
から成り立っています。
(契約期間中の解雇等)
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない理由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
<規定の趣旨と解説>
有期労働契約については、「契約社員(有期契約労働者)ならいつでも簡単に辞めてもらえる」といった誤解をしている経営者も少なくありません。このため、会社の都合で契約期間の途中で突然解雇したり、いつでも辞めてもらえるように契約期間を細切れにして契約を反復更新し、人員削減が必要になったときに雇止めにするなど、有期労働契約をめぐるトラブルも多く見られます。このような不安定な立場に置かれてしまう有期契約労働者を保護するために、労働契約法第17条で、契約期間中の解雇等についてルールを明確にしています。
また、労働契約法第17条第1項は、民法第628条「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」の趣旨を有期労働契約のルールとして規定したものですが、民法が「やむを得ない事由があるときは、契約を解除できる」としているのに対し、労働契約法は「やむを得ない事由がある場合でなければ解雇することができない」としています。つまり、労働契約法第17条第1項の規定は、民法第628条の規定を裏返したような規定ぶりになっています。これは、契約期間中の雇用保障が原則であることを強調したものです。
なお、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理(労働契約法第16条)における、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合よりも「狭い=厳格」と解されています。
それに、経営者が解雇する場合は、従来どおり、民法第628条の規定を根拠として、「やむを得ない事由」があることを、経営者側が主張・立証しなければなりません。労働契約法第17条第1項の規定が設けられても、経営者側に主張立証責任があることは、従来と変わりはないということです。
労働契約法第17条第2項における「必要以上に短い期間」とは、逆に最低どれくらいの期間が望ましいのか。私見ですが、6ヵ月以上を想定しています。
では、関連の判例を見ていきます。
有期労働契約の雇止めと変更解約告知~河合塾事件(最高裁判平成22年4月27日)
【事件の概要】
Xは、昭和56年から、学校法人九州河合塾(以下「Y法人」という。)の経営する大学受験予備校で非常勤講師として、期間1年の出講契約を締結し、平成17年に至るまで契約を更新してきた。Xが担当する講義の週当たりのコマ数(90分1コマ)は、毎年の出講契約において定められ、講義料単価に担当コマ数を乗じて講義料が支払われることになっていた。XはほぼY法人からの収入だけで生活していた。
Y法人は、毎年、受講生に対して講師や授業に関するアンケートを行っており、その結果に従って各講師の講義を評価し、出講契約を更新する際には、上記の評価が担当コマ数の割当等を行うための参考とされていた。平成15年度から同17年度にかけて、Xの評価はいずれもかなり低かったのに対し、同じ科目を担当する他の講師らの評価は高かった。Xは、平成17年度は週7コマの講義を担当していたが、Y法人は、当該科目につき評価の高い講師の担当コマ数を増やし、Xのそれを減らすこととし、平成18年度のXの担当講義を週4コマにしたい旨をXに告げた。Xは、平成18年度も従前どおりのコマ数での出講契約を求めたものの、Y法人はこれに応じず、次年度の出講契約を締結するのであれば、週4コマを前提とする契約書を返送するよう通知した。
これに対して、Xは、週4コマの講義は担当するが、合意に至らない部分は裁判所に労働審判を申し立てた上で解決を図る旨の返答をし、同契約書を返送しなかった。Y法人は、これにも応じず、契約書の返送を再度求め、返送がない場合には、Xとの契約関係は終了することになる旨通知した。Xはこれに応答せず、Y法人の担当者に契約書を提出する意思はない旨回答したため、平成18年度の出講契約は締結されなかった。
そこで、Xは、雇用契約上の地位確認、賃金および慰謝料(500万円)の支払いを求めて訴えを提起したところ、1審はXの請求を棄却した。Xが控訴したところ、原審は、慰謝料350万円の請求を認めた。そこでY法人が上告した。結果、Xの請求は棄却された。
<判決のポイント>
1 平成18年度の出講契約が締結されなかったのはXの意思によるものであり、Y法人からの雇止めであるとはいえない。
2 Xの担当講義を削減することとした主な理由は、Xの講義に対する受講生の評価が3年連続して低かったことにあり、受講生の減少が見込まれる中で、大学受験予備校経営上の必要性からみて、Xの担当コマ数を削減するというY法人の判断はやむを得なかったものというべきである。
3 Y法人は、収入に与える影響を理由に従来通りのコマ数の確保等を求めるXからの申入れに応じていないが、Xが兼業を禁止されておらず、実際にも過去に兼業をしていた時期があったことなども考慮すれば、Xが長期間ほぼY法人からの収入により生活してきたことを勘案しても、Y法人が上記申入れに応じなかったことが不当とは言い難い。
4 合意に至らない部分につき労働審判を申し立てるとの条件で週4コマを担当するとのXの申入れにY法人が応じなかったことも、上記事情に加え、そのような合意をすれば全体の講義編成に影響が生じ得ることからみて、特段避難されるべきものとはいえない。
5 Y法人は、平成17年中に平成18年度のコマ数削減をXに伝え、2度にわたりXの回答を待ったものであり、その過程で不適切な説明をしたり、不当な手段を用いたりした等の事情があるともうかがわれない。
6 以上のような事情の下では、平成18年度の出講契約の締結へ向けたXとの交渉におけるY法人の対応が不法行為に当たるとはいえない。
次も判例を見ていきます。
派遣労働者に対する中途解除の有効性~プレミアライン事件(宇都宮地栃木支判決平成21年4月28日)
【事件の概要】
労働者派遣事業を営むY会社は、自動車製造を業とするいすず自動車(以下「A会社」という。)との労働者派遣契約に基づき、同社B工場に37名の労働者派遣を行っていた。
Xは、Y会社との間で有期の派遣労働契約を締結し、平成20年10月1日に、期間を同21年3月31日までとして契約を更新して雇用されており、B工場に派遣されていた。
Y会社は、平成20年11月中旬に、A会社から同年12月26日付けで労働者派遣契約を解除するとの通知を受け、これを受けて同年11月17日付けでXら派遣労働者に対して同年12月26日をもって解雇する旨予告をした。Xらは、この解雇は無効であるとして、契約期間満了(平成21年1月から同年3月)までの賃金の仮払いを求める仮処分を申し立てた。 結果、解雇は無効と判断された。
<裁判上の判断>
1(1)「期間の定めのある労働契約は『やむを得ない事由』がある場合に限り、期間内の解雇(解除)が許される(労働契約法17条1項、民法628条)。このことは、その労働契約が登録型を含む派遣労働契約であり、たとえ派遣先との間の労働者派遣契約が期間内に終了した場合であっても異なるところはない」。
(2)「この期間内解雇(解除)の有効性の要件は、期間の定めのない労働契約の解雇が権利の濫用として無効となる要件・・・(労働契約法16条)よりも厳格なものであり、このことを逆にいえば、その無効の要件を充足するような期間内解除は、明らかに無効であるということができる」。「そこで、本件解雇の有効性について、解雇権濫用法理として、整理解雇の4要件(考慮要素)として挙げられている、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③被解雇者選択の合理性、④解雇手続の相当性の要件(考慮要素)のうち、本件に現れた事情を総合して判断することとする」。
2(1)Y会社は、A会社から労働者派遣契約を解除する通知を受けた後、Xら派遣労働者を解雇する以外の措置をなんらとっていない。Y会社が、本件のように直ちに派遣労働者の解雇の予告に及ぶことなく、派遣労働者の削減を必要とする経営上の理由を真摯に派遣労働者に説明し、希望退職を募集ないし勧奨していれば、これに応じた派遣労働者が多数に及び、そうすれば残余の少数の派遣労働者の残期間の賃金支出を削減するために、あえて解雇に及ぶことはなかったであろうと推測できる。
(2)Y会社は、Xとの派遣雇用契約書において、「派遣労働者の責に帰すべき事由によらない本契約の中途解約に関しては、他の派遣先を斡旋する等により、本契約に係わる派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする」と約定し、解雇予告通知書にも同旨の記載をしているにもかかわらず、本件解雇の予告以降、Xに対して、具体的な派遣先を斡旋するなど、就業機会確保のための具体的な努力を全くしていない。
(3)Y会社は、派遣労働者の解雇の必要性に関して、Xら派遣労働者に対して、A会社との労働者派遣契約が終了することを一方的に告げるのみであって、Y会社の経営状況等を理由とする人員削減の必要性を全く説明していない。のみならず、本件における解雇手続は、派遣労働者らに退職届を提出するよう指示するなど、有効な合意解約が成立しているとの主張を強行しており、この解雇の手続は、労使間に要求される信義則に著しく反し、明らかに不相当である。
(4)Y会社の経営状況等は相当に厳しいものと評価することができるが、他方、利益剰余金は多大で、自己資産比率も流動比率も当座比率も健在である。
では、また条文を見ていきます。
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第18条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
<規定の趣旨>
第18条第1項は、経営者の都合で反復更新を繰り返し、急に雇止めにするといった濫用的な利用を抑制し、不安定な立場に置かれる有期契約労働者を保護するため、有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」といいます。)が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより無期労働契約に転換させることができるようにしたものです。
第18条第2項は、「クーリング」を設けたのは、同一企業に再雇用されることを希望する場合に、労働者の就職選択の幅を狭めないようにするためです。
<無期転換申込権の発生要件と効果>
1)同一の経営者
2)2以上の有期労働契約
3)通算契約期間が5年を超える
したがって、労働者が無期転換を望まず、有期労働契約のまま更新していきたいという場合には、有期労働契約のまま5年を超えて6年、7年・・・と雇用を継続することは可能です。ただし、6年、7年・・・のどこでも希望すれば転換となります。
<定年後の再雇用者と無期転換について>
60歳で定年に達した後、有期労働契約で継続雇用し、通算5年を超えて契約を更新した場合、その労働者が無期転換の申込みをすれば、無期転換します。
なお、2015年4月から、同じ会社又は同じグループの会社が再雇用した人には無期転換の権利が生まれないことになります。ただし、定年退職後に転職した人については無期転換の権利は発生します。
<無期転換申込権を事前に発生させないようにすることは可能か>
無期転換申込権が発生する有期労働契約を締結する前に、無期転換申込権を行使しないことを更新の条件とするなど、有期契約労働者に事前に無期転換申込権を放棄させることはできません。有期契約労働者の雇用の安定を目的として無期転換申込権を有期契約労働者の権利として与えた法第18条の趣旨に反するからです。このような強要された有期契約労働者の意思表示(承諾)は公序良俗(民法第90条)に反して違反となります。
<カウントの対象となる有期労働契約の期間が1年未満の場合の必要な無契約期間>
2ヵ月以下 ・・・・1ヵ月以上
2ヵ月超~4ヵ月以下・・・・2ヵ月以上
4ヵ月超~6ヵ月以下・・・・3ヵ月以上
6ヵ月超~8ヵ月以下・・・・4ヵ月以上
8ヵ月超~10ヵ月以下・・・・5ヵ月以上
10ヵ月超~ ・・・・6ヵ月以上
<検討規定>
法第18条の施行日(平成25年4月1日)から5年を経過する時期(平成30年4月1日)に、同条による無期転換申込権が多く発生するものと考えられるため、この5年の経過後さらに3年を経過した時期(平成33年4月1日)に検討をすることになっています。
(有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
<法第19条の雇止め法理の対象となる場合>
1 有期労働契約が過去に反復更新され、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められる場合(東芝柳町工場事件判決を示した要件を規定)
2 労働者が有期労働契約の契約期間満了時に、契約が更新されると期待することに合理的な理由が認められる場合(日立メディコ事件判決が示した要件を規定)
<裁判例による雇止めの有効性判断の視点と雇止めが無効とされる可能性が高い事情>
① 業務の客観的内容⇒業務内容が恒常的・無期契約労働者と同じ
② 契約上の地位の性格⇒労働者の地位が基幹的
③ 当事者の主観的態様⇒継続雇用を期待させる経営層の言動があった
④ 更新の手続・実態⇒過去に契約が更新されている・更新の手続が形式的
⑤ 他の労働者の更新状況⇒同じ地位にある労働者について過去に雇止めの例無し
<不更新条項の効果>
不更新条項を経営者が一方的に提示するだけでは、それにより既に生じていた雇用継続への合理的期待を消滅させることはできないとされています。ただし、労働者が自由意思によりこれに同意した場合は合理的期待の消滅を認めるという取扱いが導けそうです。実務的には、不更新条項を明記する場合は、役割意識を自覚させ、「これができなかった場合は、更新はしない」という数値化・具体化された約定をすることが肝要かと考えます。
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
<労働条件が不合理か否かの判断要素>
① 職務の内容⇒労働者が従事している業務の内容、当該業務に伴う責任の程度
② 当該職務の内容・配置の変更の範囲⇒今後の見込みを含め、人事異動(転勤・昇進等)や本人の役割の変化等(配置の変更を伴わない職務の内容の変更も含む。)の有無・範囲
③ その他の事情⇒有期労働契約の労働者のみを短時間労働で就業させている事情・定年後の嘱託雇用として雇用している事情。
<有期労働契約基準(告示)>
基準第1条
3回以上契約を更新している者または継続勤務1年を超えている者の契約を更新しない場合には、少なくとも期間満了の30日前までにその旨を予告する。(更新しない旨をあらかじめ明示している場合を除く。)
基準第2条
3回以上契約を更新している者または継続勤務1年を超えている者の契約を更新しない場合には、労働者の求めに応じて、更新しない理由、更新しなかった理由について、証明書を遅滞なく交付する(更新しない旨をあらかじめ明示している場合を除く。)。
以上