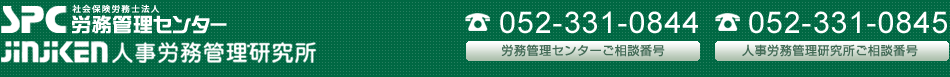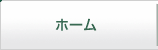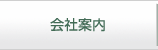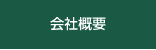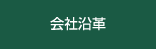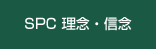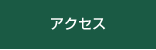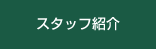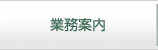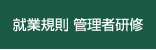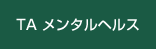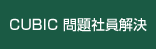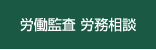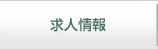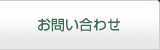■労働基準法上の労働者と労働組合法上の労働者
2016/02/21
多様化する雇用形態と労働者性の問題は、“日本ははたして安心して働ける国なのか?”というとても大切な課題と直結しています。今回は、労働者性の問題を取り上げます。
労働者性の問題は、次の三点です。
第一は、労働基準法(労基法)、労働者災害補償保険法(労災保険法)、労働契約法などの労働法の適用を受けるのか、です。
労基法9条「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義され、労災保険法の適用をうける「労働者」は、労基法の「労働者」と同一であると解されています。
労働契約法第2条「労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう」とあります。
第ニは、労働契約上の労働者であるか否か、です。
労働契約上の労働者であれば、労働保護法規の適用を受けるのみならず、労働契約法第15条、16条の懲戒権・解雇権濫用法理の適用を受けることになります。
第三は、労働組合法が適用される労働者に該当するか否か、です。
労働組合法第3条「労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう」と定義され、労働基準法の「労働者」より広く解釈されています。
労働組合法上の労働者性の判断基準(平成23年7月25日労使関係研究会厚生労働省)
<基本的判断要素>
1.事業組織への組み入れ
2.契約内容の一方的・定型的決定
3.報酬の労務対価性
<補充的判断要素>
1.業務の依頼に応ずべき関係
2.広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
<消極的判断要素>
1.顕著な事業者性
また、労働者が労基法9条の「労働者」に該当するかの判断として、労働基準法研究会が昭和60年(1985年)12月19日付で「労働基準法の『労働者』の判断基準について」を出しています。
1.業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容
2.支払われる報酬の性格・額
3.使用者とされる者と労働者とされる者との間における具体的な仕事の依頼・業務指示等に対する諾否の自由の有無
4.時間的及び場所的拘束性の有無・程度
5.労務提供の代替性の有無
6.業務用機材等機械・器具の負担関係
7.専属性の程度
8.使用者の服務規律の適用の有無
9.公租などの公的負担関係
10.その他諸般の事情を総合的に考慮
それでは、はじめたいと思います。
取り上げる最高裁判例は、次のものです。
労働基準法上の労働者~藤沢労基署(大工負傷)事件(最高裁平成19年6月28日判決)
労働組合法上の労働者~INAXメンテナンス事件(最高裁平成23年4月12日判決)
藤沢労基署(大工負傷)事件-「労働基準法上の労働者」
大工であるXは、1人で工務店の大工仕事に従事するという形態で稼動していた。Xは、平成10年3月頃からA社の仕事をするようになったが、XとA社との間では、請負・雇用等の契約書は作成されていなかった。Xは、A社の就業規則の適用を受けず、A社を事業主とする労働保険・社会保険の被保険者にもなっておらず、国民健康保険組合の被保険者であった。A社がXに報酬を支払う形態は、稼動した日数に応じて日当を支払う「常用」と、1㎡当たりの単価を決め、内装工事をする部屋の広さにその単価を乗じて支払う、出来高払い方式の「請負」とがあったが、「請負」形式が中心であった。Xは、いずれの形式の場合も、A社に対して請求書を発行し、それに応じてA社の支払がなされていた。A社は当該支払について、給与所得にかかる給与等として所得税の源泉徴収の扱いをしていなかった。
Xは、B工務店等の受注したマンション建築工事についてA社が請け負っていた内装工事に従事していた際に、右手の指3本を切断する災害に遭ったため、業務に起因したものであるとして、管轄のY労基署長に対して労災保険法に基づき療養補償給付と休業補償給付の請求をしたが、Yは、Xは労災保険法上の労働者にあたらないとして不支給処分を行った。
Xの就労の実態は、次のようなものであった。(イ)A社から寸法、仕様等につきある程度細かな指示を受けていたものの、工法や作業手順は自分の判断で選択することができた。(ロ)Xは、作業の安全確保等から所定の作業時間に従って作業することを求められていたものの、事前にA社の現場監督に連絡すれば、工期に遅れないかぎり、休むことができるし、作業を所定の時刻より遅く始めたり早く切上げたりすることは自由であった。(ハ)A社はXに対して、他社の仕事を禁じてはいなかった。(ニ)Xは、本件工事において、自ら所有する一般的大工道具一式を現場に持ち込んで使用し、A社の所有する工具を使用するのは特殊な工具に限られていた。(ホ)Xの本件工事についての報酬は、約月50万~70万円程度と、A社従業員の給与よりも相当高額であった。(ヘ)A社は、本件工事の現場監督が多忙であったことから、Xに対して職長業務を行ったほしいと依頼し、月額20万円の職長手当の支給を約束した。(ト)本件工事に際し、B工務店はXら大工に労災保険法35条に基づく特別加入を勧めたが、Xは加入しなかった。
一審は、これら諸事情から、Xは労基法上、労災保険法上の労働者に該当しないとしたため、Xが控訴。二審も一審判決を引用しXの労働者性を否定して、さらに一審判決に補足したうえで、Xについて、使用従属関係と労務提供に関する賃金の支払関係のいずれについても、その存在を肯定できないとして控訴を棄却した。Xが上告し、最高裁は上告を棄却した。
<判決からのメッセージ>
「Xは、前記工事に従事するに当たり、B工務店はもとより、A社の指揮監督の下に労務を提供したいたものと評価することはできず、A社からXに支払われた報酬は、仕事の完成に対して支払われたものであって、労務の提供の対価として支払われたものとみることは困難であり、Xの自己使用の道具の持込み使用状況、A社に対する専属性の程度等に照らしても、Xは労働基準法上の労働者に該当せず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないというべきである。Xが職長の業務を行い、職長手当の支払を別途うけることとされていたことその他所論の指摘する事実を考慮しても、上記の判断が左右されるものではない。」
→①仕事の内容について、具体的な工法や作業手順について指定を受けることなく、自分の判断で選択していたこと。②工期に遅れない限り、仕事を休んだり、所定の時刻より後に作業を開始したりするなどの自由があったこと。③報酬は完全な出来高払い方式が中心とされ、請求書によって報酬を請求しており、その額もA社従業員より相当高額であったこと。④一般的に必要な大工工具一式を自ら所有し、これを現場に持ち込んで使用していたこと。⑤就業規則の適用を受けず、A社を事業主とする労働保険や社会保険の被保険者となっておらず、報酬についても給与所得として所得税の源泉徴収をする取扱いがなされていなかったこと。などの事実に基づいて、「指揮監督の下に労務を提供していたものと評価することはできない」し、「報酬は労務の対価に支払われたものとみることは困難」であり、「自己使用の道具の持込み使用状況、専属性の程度等に照らしても」、労働者とは認められないと判断した。
<メッセージに対する私的見解>
A社はXと「業務委託契約」を締結し、Xに対して、「一人親方ですよ。労働者ではありませんよ。事故が起こった場合は、特別加入しなければ特に治療費は補償されませんよ」と力説するべきであったと思います。また、業務委託契約の条文として、X本人に過失があった場合は、A社に対して損害賠償請求しない旨も明記しておくべきであると考えます。
INAXメンテナンス事件-「労働組合法上の労働者」
本件は、住宅設備機器の修理補修等を業とする会社であるX社が、X社と業務委託契約を締結して修理業務に従事するカスタマーエンジニア(CE)が加入した労働組合から労働条件の変更等を議題とする団体交渉の申し入れを受けたのに対し、CEは労働者に当たらないとして申し入れを拒絶したところ、中央労働委員会が同社に団体交渉に応じるよう命じたため、この命令の取り消しを求めて提訴し、一、ニ審で判断が分かれていた。
一審判決は、労組法上の労働者は単に雇用契約によって使用される者に限定されず、他人(使用者)との間において使用従属関係に立ち、その指揮監督のもとに労務に服し、労働の対価としての報酬を受け、これによって生活する者を指すと解するのが相当であるとして、X社の主張を退け、CEは労組法上の労働者に当たるとしたうえ、組合からの団交申入れを拒否したX社の対応は労組法7条2号に該当する不当労働行為であり、これを認めた本件救済命令が違法とはいえないとしてX社の請求を退けた。X社が控訴。
二審判決は、業務依頼に対する諾否の自由、時間的場所的拘束、具体的な指揮監督、報酬の性質などの点から、CEの基本的性格はX社の業務受託者であり、いわゆる外注先とみるのが実態に合致しているとして一審判決を取り消し、本件救済命令を取り消した。これを不服として上告。最高裁は、二審判決を破棄した。
<判決からのメッセージ>
最高裁は、
1.CEはX社の事業に遂行に不可欠な労働力としてX社の組織に組み入れられていたこと。
2.業務委託契約の内容はX社が一方的に決定していたこと。
3.CEの報酬はその額の決定方法から労務の提供の対価しての性質を有しているといえること。
4.CEは基本的にX社による個別の修理補修等の依頼に応ずべき関係にあったこと。
5.CEはX社の指定する業務遂行方法に従い、その指揮命令の下に労務の提供を行っていたこと。
6.業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていたこと。
などを認めたうえで、これらの事情を総合的に考慮して、CEはX社との関係において労働組合上の労働者に当たるとするのが相当であると判示した。
→1.事業組織への組み入れ
2.契約内容の一方的・定型的決定
3.報酬の労務対価性
4.業務の依頼に応ずべき関係
5.広い意味での指揮監督下の労務提供
6.一定の時間的場所的拘束
<メッセージに対する私的見解>
労組法上の労働者として判断されたら実務上どうなるのか?団体交渉はすることになります。ストライキ権を行使されることもあるかもしれません。かといって、組合の要求を呑まなければいけないわけではありません。あくまでも交渉に時間を費やされるだけです。労基法上や労働契約法上の労働者に該当すれば、労働時間法制、解雇法制の適用がのしかかってきますが、労組法上の労働者とされることの実害は経営者にとっては重すぎることはないといえそうです。
次に昨今の事件ですが、取り上げるのは次の判例です。
労働組合法上の労働者~新国立劇場運営財団事件(東京地裁平成23年4月12日判決)
新国立劇場運営財団事件-「労働組合法上の労働者」
上告組合は、職業音楽家と音楽関係業務に携わる労働者の個人加盟による職能別労働組合である。被上告財団は、年間を通して多数のオペラ公演を主催している。被上告財団は、毎年、オペラ公演に出演する新国立劇場合唱団のメンバーを試聴会を開いて選抜し、合格者との間で、年間シーズンの全ての公演に出演可能である「契約メンバー」と、被上告財団がその都度指定する公演に出演することが可能である「登録メンバー」に分けて、出演契約を締結していた。
Xは上告組合に加入し、新国立劇場合唱団の契約メンバーとして、平成11年8月から同15年7月まで、毎年、出演基本契約を締結し個別公演に出演していたが、平成15年2月20日、同年8月から始まるシーズンについて、契約メンバーとしては不合格であると告知された。
上告組合は、平成15年3月4日、被上告財団に対し、次期シーズンの契約に関する団体交渉を申し入れ、被上告財団は、同月7日、Xとの間に雇用関係がないことを理由に団体交渉を拒んだ。一審(東京地判平成20年7月31日)、二審(東京高判平成21年3月25日)が、不当労働行為性を肯定した中労委命令を取り消したため、組合が上告した。最高裁は、労組法上の労働者と判示した。
<判決からのメッセージ>
「出演基本契約は、被上告財団が、各公演を円滑かつ確実に遂行することを目的として締結されたもので、1.契約メンバーは、各公演の実施に不可欠な歌唱労働力として被上告財団の組織に組み入れられていた。2.契約メンバーは、出演基本契約を締結する際、被上告財団から、全ての個別公演に出演するために可能な限りの調整をすることを要望されており、出演基本契約書には、年間シーズンの公演名等が記載されていた。3.契約メンバーは、被上告財団の指定する日時、場所において、その指定する演目に応じて歌唱の労務を提供していた。4.Xが新国立劇場に行った日数は、平成14年8月から同15年7月までのシーズンにおいて約230日であった。5.契約メンバーは、出演基本契約書の単価及び計算方法に基づいて計算された報酬の支払いを受け、超過稽古手当も支払われており、報酬は年間約300万円であった。」
→1.事業組織への組み入れ
2.業務依頼に応ずべき関係
3.契約内容の一方的決定
4.労務遂行に当たっての指揮監督関係や時間場所的拘束
5.報酬の労務対価性
<メッセージに対する私的見解>
まさしく、労組法上の「労働者」に当たるとした、INAXメンテナンス事件(最高裁判決平成23年4月12日 判決日同じ)と同様な要素を基に判断をしています。ただ、今回も労基法上の労働者として認められたわけではないので、労基法で定める労働者の権利(労働時間・年次有給休暇・解雇予告手当等)を享受することはできません。何の為の訴訟なのか?あわよくば、労働契約上の地位確認が勝ち取れればとの本音が見え隠れしますが、最高裁は、労組法上の「労働者」は、労基法・労働契約法上の「労働者」とは異なることを前提としているみたいです。経営サイドにとっては、「ほっと」する点です。
最後に、藤沢労基署(大工負傷)事件、INAXメンテナンス事件、新国立劇場運営財団事件を通していえることですが、労基法上の「労働者」が生存権(憲法25条)「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を基盤とする労働条件の最低基準の適用によって保護を受ける者であるのに対し、労組法上の「労働者」は、「労使対等の交渉を実現すべく、団体行動権の保障された労働組合の結成を擁護し、労働協約締結のための団体交渉を助成することを目的とする」(労組法1条)を基盤としています。換言するならば、使用者と対等な立場に立って、その地位を向上させるために、団結し、団体交渉や団体行動をすることが予定される者です。このように両者は立法目的が異なります。ゆえに学説上、労組法上の「労働者」は、「労働契約によって労務を供給する者およびこれに準じて団体交渉の保護を及ぼす必要性と適切性が認められる労務供給者」を意味すると主張されています(菅野和夫著「労働法」)。
私見的には、上記のことも大切ですが、“日本ははたして安心して働ける国なのか?”を検討すべき成熟期にきていると痛感します。働いている人達が、そのニーズに応じて法的な保護を得られるようにするにはどうすればいいのか?大きな課題です。
以上です。