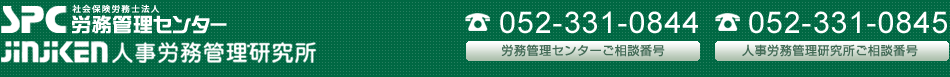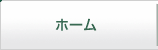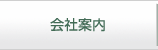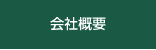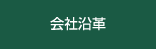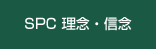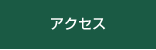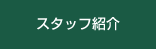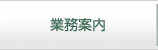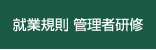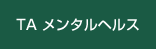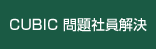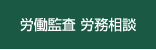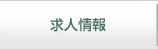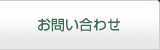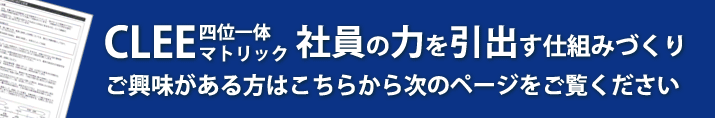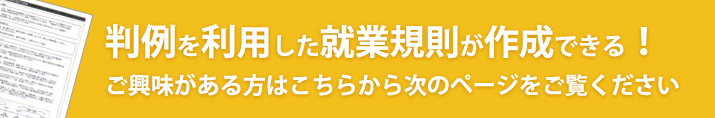海外留学終了後に退職、費用3000万円返還求める
2021/11/05
みずほ証券事件 【東京地判令和3年2月10日】
【事案の経緯・概要】
H23.4 従業員甲の入社 H26.10 会社の公募留学制度に応募
H27.1 公募留学生として選抜 H28.7~H30.5まで留学
H30.6.10 帰国 H30.10.31 退職
●会社の公募留学制度の目的
国際的視点に立った視野の広い人材の育成、グローバルな環境下でリーダーシップを発揮できる人材の育成
●誓約書の内容
留学期間中または留学終了後5年以内に特別な理由なく退職する場合あるいは解雇される場合は、留学に際し会社が負担した留学に関する以下の費用を退職日までに遅滞なく弁済することを誓約する
●留学費用30,450,219円を会社側が返還請求 消費貸借契約を主張
●判決 会社側勝訴
【判決のポイント】
【争点】
1・消費貸借の成否(留学費用に関する合意の有無)
<民法第587条 消費貸借>
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
〇会社が留学制度を設ける趣旨
- 海外勤務のために語学留学をさせるなど,会社の業務として設けている場合
- 社員のキャリア形成を援助し,社員としてのモチベーションを高めることを目的としている場合
- であれば,留学自体が会社の業務であり,その費用を社員が負担することはない。
- であれば,留学によって受益するのは,直接的には社員自身であるので,会社は,留学中も給与を支払うものの,その留学費用を当然に負担すべき義務があるわけではない。
留学期間は年単位のケースもあり、渡航費・滞在費・授業料など相当の費用がかかるため、企業としては、「投資」した従業員にはできるだけ長く勤めてもらいたい。
そこで、留学するにあたって、あらかじめ「一定の期間内に自分の都合で退職した場合は、会社に留学費用を返還する」などと約束させることがある。
2・返還合意が労基法16条に違反しているかどうか
<労働基準法16条>
使用者は労働契約の不履行について違約金を定め損害賠償額を予定する契約をしてはならない→返還合意により労働者の自由意思を不当に拘束することを許さないという趣旨
労働基準法16条に違反するかの判断基準
〇返還義務を就業規則と一体となる留学規程等で定めただけで、別途合意書や誓約書を作成しなかった場合は、労働契約上の義務違反を理由とするものであり、労基法16条に違反すると判断される可能性が高い(新日本証券事件・東京地裁平成9年5月26日判決)。ただし、合意書や誓約書を作成すれば、ただちに返還義務が認められるというわけではなく、合意書や誓約書から、留学費用は消費貸借契約に基づき貸与するものであることや、留学後一定期間の勤務はこの消費貸借契約により発生した債務を免除するものであることを明確に読み取れるようにすることが必要である。条件次第で免除されるが、原則、借金であると明示しておくことが大事である。
〇留学の業務該当性の判断
留学が業務の実質を有しているか、具体的には、留学が従業員の自由な意思に基づいたものか、留学で学んだことが従業員の担当業務と直接の関連性がないか、などの事情を考慮し、留学の「業務該当性」が判断されることとなる。(野村證券事件・東京地裁平成14年4月16日判決、明治生命保険事件・東京地裁平成16年1月26日判決)。
〇返還義務が免除される要件の勤務期間が長すぎる場合
返還が免除されるまでの勤務期間が不当に長い場合にも、労働者を不当に拘束するものとして、労基法16条の趣旨に反すると判断される可能性がある。
この点については、みずほ証券事件、野村證券事件、明治生命保険事件とも、免除されるまでの期間が5年というケースであったが、裁判所はこの期間を特に問題視しなかったので、「5年」までであれば、労基法16条違反の問題は回避できる可能性が高いと思われる。
【SPCの見解】
労働基準法16条では”労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。”と大原則があります。
労働契約の不履行の場合の違約金制度の設定
例)「途中でやめたら、違約金を払え」
労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む
例)「会社に損害を与えたら○○円払え」
上記事項を禁止しています。
本判決においては、本来、労働者本人が負担すべき自主的な留学費用について、業務性を有するものではなく、労働者自身が自主的に制度を利用したものとされています。
また、返還義務免除期間も5年とされており、不当に長いものではありませんでした。長期間に及ぶと、労働者の就労の自由を不当に拘束すると判断される場合もございます。
本件のような留学費用だけでなく、資格取得に関わる費用や大学生在籍時の学費補助など、会社が労働者に対して貸付を行っている場合は、業務性を有すものでないことや返還義務が免除される期間を不当に長いものにしないなどを注意して頂き、適正な制度運用に努めてください。