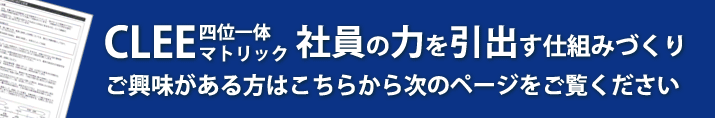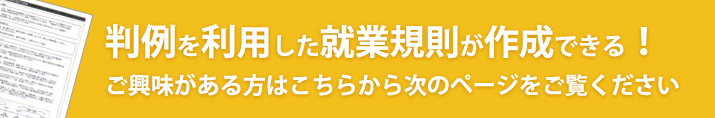一般職が社宅の利用認められず損害賠償求める
2025/02/04
AGCグリーンテック事件【東京地判 令和6年5月13日】
【事案の概要】
一般職の女性(X)は、現在は全員が男性社員の総合職に家賃を最大8割補助する社宅制度がある一方で、女性が大半を占める一般職には月3,000円の住宅手当のみは、男女差別で違法だとして会社(Y社)に対して損害賠償などを求めた。
Y社は、1999年の設立時から2020年までに在籍した総合職計34人のうち、女性は1人のみだった。一方で、一般職は計7人のうち女性が6人であった。
Y社の社宅制度は、当初は総合職に対して転居を伴う転勤命令がなされた場合に限って適用される制度であったが、およそ通勤圏に自宅を保有しない総合職であれば適用されるとする運用に変更を行った。
【判決のポイント】
(1)直接差別について
社宅制度に関する取り扱いについては、直接的に男女の性別により差別しているとは認められず、社宅制度の利用を受けてきたのが1名の女性を除き、全員男性であったという外形的事実からも直接差別であると推認することはできない。
(2)間接差別について
均等法7条により、性別以外の事由を要件とするもののうち、実質的に性別を理由とする差別になるおそれがある措置として厚生労働省令に定めるものは、業務の性質に照らして必要である場合などでなければ、これを講じてはならないとされています。
Y社の社宅制度は総合職であれば適用され、そのほとんどは男性で構成されていた。また、社宅制度を利用できるかどうかで享受する経済的恩恵の格差はかなり大きいことが認められる。
このような社宅制度を総合職に限って適用する必要性や合理性を根拠づけることは困難であり、均等法の趣旨に照らして間接差別に該当するというべきである。
なお、本判決は控訴等なされず、地裁判決で確定しています。
【SPCの見解】
Y社の社宅制度は、当初は転居を伴う転勤命令がなされた総合職に限って適用されていましたが、およそ通勤圏に自宅を有しない総合職にまで適用される幅を広げ、転勤の現実的可能性がない者に対しても社宅貸与を行ったことから、男女差別に該当するのではないかと提訴されてしまうことになりました。
この適用の幅を広げた際に、一般職の住宅手当との差を精査できるチャンスであったとも言えます。
結果として、Y社は慰謝料など約378万円の賠償を命じられました。
近年は、直接差別はあまり聞かないものの、間接差別(合理性のない身長、体重、体力や転居された経験など)は判断がしづらく、長年の慣習によって行われている事例も多くあります。
特に手当などの差は後々の金銭的な負担増など経営にも影響するため、慎重に検討することが求められます。